前回「ひきこもり放浪記 第6回」で述べたように、
私の「移動性ひきこもり」の歳月は、
移動と滞留から成り立っていて、
前回は移動について掘り下げてみたわけだが、
今回は滞留という体験について書かせていただきたい。
まったく思ってもみない土地で、すっかり足止めをくうことがある。
そのような場所にかぎって、生涯わすれがたい体験をしたりする。
アフリカ大陸の北半分を占めるサハラ砂漠のど真ん中、
ワディハルファという小さな村が、私にとってそんな舞台となった。
村といっても、きわめて荒涼としており、
土を固めてつくった家々が、
見渡すかぎりの砂の曠野(こうや)に、あちこち点在しているだけであった。
世界でも最も貧しい国といわれるスーダンの入り口にあたる。
それでも、村の中には鉄道の起点があって、
首都ハルツームへ向けた2泊3日の長距離列車が
そこから週1便出るはずであった。
ところが、掘っ立て小屋のような駅舎を訪ね、駅長に訊いてみると、
機関車のどこかが壊れたとかで、いまは列車は出ないという。
「いつ直るのか」と尋ねても、駅長は、
「わからない。首都から修理の部品を取り寄せている最中だ。また来てみてくれ」
というのみである。
日本では年号が平成に切り替わったその年、
インターネットも携帯電話もまだない。
固定電話ですら、その村にはないに等しかった。
電話機は村に一、二台あるが、
砂漠を横切るあいだに電話線が切れているのか、
いつも不通なのである。
陸の孤島。
地図で見ると、
大海原のように平らかだと錯覚されるサハラ砂漠には、
じつはかなりの凹凸があり、高低差がある。
丘があり、川があり、山があり、谷がある。
ただし、水は一滴も流れていない。
水がないということは、生がないということだ。
地表から深さ2メートルほどまでは、無菌状態だという。
強烈な紫外線と、フライパン並みの加熱により、
つねに殺菌されているのである。
宇宙空間さながらに、
生き物の営みを峻厳に拒絶する鉱物的世界。
さしたる備えもなく、そんな砂漠の只中へ突き進むことは死を意味する。
イスラムの国々は、よく三日月を国旗に掲げるが、
それは砂漠において太陽は死であり、月が生の源であるからだ。
もともと暑さに弱い私は、
地球上で最も滞留したくない村で足止めをくらったようであった。
天気予報がいらない
ここでは、天気予報が要らなかった。
空は、毎日のように快晴で、気温も規則正しく上下する。
日が昇るとともに、温度はぐいぐいと上がり、
8時頃には、すでに日本では盛夏の陽ざかりの気温となる。
10時ごろには軽く40度を超え、
温帯動物である私は、もう何もする気がなくなるのであった。
午後2時ごろに、いつもその日の最高気温、54度を記録し、
そこでコーナーを回って気温はおもむろに下がっていくのだが、
夜になっても、なおも空気は暑熱をはらみ、
とても寝つける環境がととのわない。
夜半をすぎ、午前3時をすぎ、明け方近くなって、
ようやく気温は20度近くまで下がり、
温帯の国からやってきた私はほんらいの活力を取り戻し、
その力をすぐさま睡眠をとることへ注ぎこむのだが、
眠りがまともな深さをえぐる前に、
またしても灼かれるような周囲の暑さに起こされることになるのである。
命拾い
駅長は、「また来てみてくれ」と事もなげに言う。
たしかに、宿から鉄道駅までは、
地元の人の足で5分ほどの距離だから、
他にすることのないこの村では、ちょくちょく顔を出すのが順当なのだろう。
けれども、異邦人の私が行けば30分はかかるのである。
猛烈な暑さに、息が切れる。
砂嵐がやってくれば、
もう目を開けていられず、進むのをあきらめ、
嵐が去りゆくまで何分かをその場で立ち尽くすことになる。
そのあいだも体内から水分がまたたく間に蒸発していき、
皮膚には塩の結晶ができていく。
私は焦熱地獄を突っ切る覚悟で、
またしても昼日中に宿を出て、小さな駅舎へ向かった。
そのうちに意識が朦朧としてきて、
歩いても、歩いても、めざす駅舎が近づいてこなくなった。……
気がつくと、
白い天幕のような屋根のある、
日陰に寝かせられていた。
私のかたわらには、
顔に刺青をして、上半身は裸で、槍を持っている
土着の民族、ヌバ族の若者が座っていた。
どうやら私は、脱水症状で意識を失いかけ、
駅や宿とはまったく異なる方向、
すなわち砂漠のど真ん中へ歩をすすめていたらしい。
熱砂の中にさまよっていた私を、
この若者は見つけ、怪訝に思い、天幕へ引っぱってきて、
バケツに水を汲み、この地方では貴重な海塩を少し中に溶かし、
私の首をつっこんで飲ませてくれたのである。
それで何の見返りを求めるでもない。
純朴で、正義感のある、まっすぐな男であった。
私は、彼に命を救われたのである。
謎のいざない
放浪者は、さまざまな土地の言葉を
片っ端から憶えては忘れていくものである。
イスラム圏に入ってから、
私もカタコトのアラビア語を話すようになっていた。
ヌバ族の彼にとっても、アラビア語は外国語であり、カタコトである。
カタコト同士であるからこそ、
かえって意思の疎通が開通したように思う。
親しくなった彼を、私は自分の宿部屋へ招き、
いろいろな話をするようになった。
来る日も来る日も列車は出ない。
時間だけは豊富にあった。
同じくらいの齢の男同士、話題も尽きなかった。
かたや文明国で育ったひよわなアジアの男、
かたや裸で暮らす屈強なアフリカの男。
しかし、人生について考えていることは驚くほど似ていたのである。
そのうち、彼が「酒を飲みたいか」などと私に問う。
私は目をみひらいた。
「酒が、この村にあるのか?」
イスラム圏に入ってから、ながらく酒を飲んでいなかった。
イスラムの国でも、国情によっては、
おおっぴらに飲めたり、コソコソと飲めたりもするが、
戒律が厳しいスーダンでは、まったく飲めないことになっている。
しばらく前に、首都ハルツームでワインを隠し持っていたイタリア人が
高級ワインをすべて没収されナイル川へ流されたすえ、
公開むち打ちの刑に処せられたという話があった。
そんな目にあうのは、ごめんである。
しかし、それをいうと、
「大丈夫だ。ハルツームは都会だから、そうなるんだ。
ここはスーダンの中でも端の端、地の果てだ。
それに、アラブ人たちに言わなければ、わからないよ」
と彼はいう。
ヌバ族の彼にとって、イスラム教徒であるアラブ人は
北から侵入してきた統治民族にすぎないのである。
アラブ人の禁忌は、彼にとって禁忌ではない。
だが、どこに酒があるのか。
バーも居酒屋もない。
コーラですら年に数回しか入ってこないのである。
「おれについてこい」
ヌバ族の若者は、私の先に立って歩き始めた。
すでに陽がかたむき、温帯動物である私も動き回れる時間帯となっていた。
どこへ連れて行くのか。
カタコトのコミュニケーションでは説明しきれない何かがあるのか、
彼も言おうとしない。
やがて彼の足は村の中央から離れていった。
砂丘のまっただ中に突き進んでいくのである。
「おい。どこへ行くんだ。村が遠くなってしまうぞ」
後ろから呼びかけたが、私の声は砂紋をえがく風の音にかき消されてしまう。
一つの砂の丘を越えると、
またしても色も形も大きさも同じような砂の丘が
その向こうにあらわれる。
またしても丘。
またしても丘。
サハラの自然は、過酷にして単調である。
やがて、丘の麓の窪地に、
かなり薄汚れて砂地と同じ色になったテントのようなものが見えてきた。
「あそこだ」
ヌバ族の若者は、たくましい褐色の腕を上げて指さした。
私はテントを見つめた。
そこで私は
おそらく生涯わすれないであろう、
一人のひきこもりと出会うことになるのである。
・・・「ひきこもり放浪記 第8回」へつづく
紙面版ご購入はこちらをクリック
サポート会員募集中!詳細はこちら
更新情報が届き便利ですので、ぜひフォローしてみて下さい!
Twitter
Facebookページ
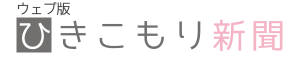


読ませますね。続きに期待します。
地図とかもつけてくれるとありがたいです。
この「ひきこもり新聞」web 版には、ブロゴスブロガー「ニャート」さんのブログからサーフしてやってまいりました。
職業はありますが、ときどき急に働けなくなります。その間はまったくの引きこもり状態に近いです。
もちだともひこさま コメントをどうもありがとうございます。
私は確認できませんでしたが、私どもの「ひきこもり新聞」を、ニャートさんという方はご紹介くださっているのですね。まことにいたみいります。
地図をつけたら、というご意見は、たいへん参考になりました。
今後、検討させていただきます。ありがとうございました。