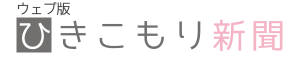前回「ひきこもり放浪記 第8回」でお話しした
エチオピア貴族の紳士との出会いがあってからも、
首都ハルツームへ発つ列車は、いまだ出る気配はなかった。
サハラ砂漠の真っ只中の辺境の村、
ワディハルファで足止めをくらった私は、
毎日、昼は54℃まで気温があがる、この灼熱の地での
暮らし方というものを次第に体得していかざるをえなかった。
暑熱がつのる日中には、
外を出歩くことはもちろんのこと、
室内においても、そもそも
「何かをする」という野心を捨てるのだ。
何もしない。
ただ生きている。
せいぜい、ときどき水を飲むくらいである。
それをよしとする。
たとえ人から何を言われても。……
これは、うつ病という宿痾(しゅくあ)を持った私には、
よいレッスンであったかもしれない。
この地に適した低燃費な生き方に慣れると、
ふしぎと体力も戻ってきた。
陽が西へかたむき、気温が日本の夏ぐらいにまで下がってくる夕暮れどきに、
私は砂漠の散歩に出かけるようになった。
いくつか砂の丘を越えたところで、
ふと、向こうに人影を認めた。
夕食どきに、優雅に散歩などしているのは、
ここの住民ではない。
目をこらすと、どうやら東洋人のようである。
先方も、私の姿を認めた。
そして、大声で何かを言った。
中国語のようであった。
当時の私は、中国語がまるでわからない。
相手は、英語もアラビア語もわからないようである。
そこで、私が中学高校で習った漢文だけが
唯一のコミュニケーション手段となった。
沈みゆく太陽の光にじりじりと頬を灼かれながら、
私たちは、片方を軸足として、もう片方の足で砂地に漢字を書き、
自分の身長の何倍も長い文章をつらねて筆談をした。
学校の黒板とちがって、書く面積は無限にある。
アフリカ大陸に、でかでかと東洋の文字が書かれていった。
ときおり吹き抜ける強風に、
たちまち半分ほど掻き消される文字もあった。
はじめは、お互い言いたいことが通じ合えなかったが、
ひとたび文脈を得ると、
急速に具体的なことまで話は深まっていった。
相手の意味することが不確かな場合は、
「それは、こういうことか?」
と私なりにパラフレーズして顔色をうかがう。
「トゥイ、トゥイ(そう、そう)」
と男は口から発しながら、またたくさんの文字を書き足していくのであった。
文化大革命の吹き荒れた成育歴
劉は、ようするにエリート技師であった。
中国一の先進都市、上海に生まれ育った彼は、
成長期を文化大革命(*1)が襲った。
文字通り「文化的」な家系であり、
彼の両親はともにオーケストラの団員であったが、
西洋ブルジョワジーの音楽を演奏したとの廉(かど)で
辺鄙(へんぴ)な地方、江西省の山の中へ下放(*2)された。
劉自身はまだ幼かったので下放されず、
上海にとどまり、祖母に育てられたが、
まともな教育は受けられなかった。
まともな教育を受けること自体が、
資本主義に走る行為として批判される時代であった。
批判の対象となれば、町のさらし者になり、
心身ともにボロボロになった。
しかし、文化大革命の最中も、
発禁された書物を悪友たちと回し読みすることによって、
こっそりと知識を習得することはできたという。
彼らにとっては勉強が、最大の不良行為であったのだ。
1976年、文革の頂点に君臨した毛沢東(マオツオトン / もうたくとう)が死去し、
カリスマの傘にかくれて
権力をほしいままにしていた四人組が逮捕された。
やがて鄧小平(トンシャオピン / とうしょうへい)の時代になって、
中国は改革開放へと国家経済の舵を大きく切った。
下放されていた人たちも自分の都市へ帰ることができ、
生徒や学生たちもあわただしく勉学へ戻った。
劉は、英語を習得する機会もないままに、
理工系の大学へ進むことになる。
経済発展が許されたということは、
劉にとって自分を生きることが許されたということであった。
1980年代、中国国内の経済が活況を呈してくると、
政府はアフリカなど貧しい国々への覇権を樹立することに躍起となりはじめた。
そのとき、目標としたのが日本だったのだという。
それまで、発展途上国の支持票は、
日本が一手に集めていた感があった。
高度成長期の日本は、
小さな国でありながら、
国連などの大舞台でアジア・アフリカ諸国などから大量に得票するのを、
一種のお家芸としていたのである。
経済大国として後発組となった中国は、
日本のやり方をまねて、国際舞台で力を持つために、
途上国援助を積極的に国策に取り入れ始めたというわけである。
国運を賭けた対外プロジェクトがいくつも立てられ、
エリート技師らが中国国内から掻き集められ、
世界の辺境へ送り出された。
最貧国と呼ばれたスーダンにも、
中国人技師の一団がやってきた。
劉は、なかでもとりわけ嘱望されたのか、
最前線基地となるサハラ砂漠のど真ん中、
ワディハルファから2キロ離れた、
ナイル川沿いのテントに送りこまれたのだという。
ひと昔前は「白人の墓場」と称されたこの酷熱の地に、
もう一年も前からテント生活をしていると知り、
私はにわかに劉を尊敬した。
皮膚にある汗腺の数もアフリカ人とはちがう、
私たち東洋人がそう簡単にできることではないのである。
地元の民、アラブ人やヌバ族とも交流せず、
何か一つのミッションに集中しているらしい。
やっていることの内容は、
国家機密の端くれなのか、教えてくれなかった。
外へ、外へとひきこもる
そのかわり劉は、
太陽が傾きかけた黄土色の大地に、でかでかと足で
「到外面」
と書いた。
また何を言おうとしているのか、わからない。
私は、首をかしげて見せた。
すると、劉はおもむろに文頭へ立ちまわって、
いくつかの文字を書き足した。
「我们走出去到外面」
どうやら
「われわれは外へ出ていくのだ」
という決意表明のようである。
劉は、口の端をねじまげてニタリと笑い、
どこか挑発的に私の反応をうかがっている。
「お前たち日本人に負けないぞ」
という意思がこめられているようだ。
サハラの西日に照らされた彼の顔は、
漢民族らしい旺盛な商魂がかがやいているように見えた。
そんな挑戦を受けて立つ気などさらさらなく、
もともとアフリカには「死ぬ気」で来ている私は、
大きな戸惑いを隠せなかった。
国家戦略の最前線として、
アフリカのこんな奥地に送りこまれている、ということが、
劉にとっては誇らしくて仕方がないらしい。
外へ出ていくことが禁じられた時代に成長期をすごしたために、
なおさら外へ出ていくベクトルは、
劉の心のうちにおいてたくましく膨張したのだ。
わからないことはない。
自由な好奇心も、闊達な挑戦も、
すべてが封じこまれ、禁じられていたであろう、
劉が青春をすごした文化大革命の時代。
いま改革開放の波に乗って、そのころの反動が爆発している。
彼らは、外へ、世界へ、出て行こうとしている。
しかし、外へ外へと出ていった先が
サハラ砂漠のど真ん中なのである。
私は、前回「ひきこもり放浪記 第8回」で触れた、
同じ村の砂丘の陰にひっそりと暮らしている
エチオピア人貴族のことを想った。
こうして私と劉が話しているあいだも、
いくつか砂丘を越えた向こうで、
あの紳士は今日も密造酒をつくり、
ひきこもりの一日を送っていることだろう。
「やっていることは同じ」とは言わないまでも、
持っている意識の方向性をのぞけば、
彼ら二人の生活のかたちは結果的にとてもよく似ているのではないか。
砂漠の奥地で、よけいなものを切り捨て、
人とあまり交わらず、孤立して生きている。
そういう生の様態を、
あの紳士は「ひきこもり(withdrawn)」と言い、
劉は「外へ出ていく(到外面)」と言う。
ずっと表をたどっていくと、
いつのまにか裏になっているメビウスの輪のように、
ひきこもりと反ひきこもりの極致が、
いつのまにか同じ形になっている。……
陽が落ちた。
今夜はまだ月が出ない。
街灯など一つもないサハラ砂漠では、
暗くなると、異邦人は村へ帰れない。
私たちは砂上に書いた広大な筆談を打ち切り、
それぞれの方角へと帰っていったのであった。
・・・「ひきこもり放浪記 第10回」へつづく
<註>
*1.文化大革命(ぶんかだいかくめい):「文革」と略称される。中華人民共和国において1966年から1976年まで起こった社会的騒乱。名目上は「封建的文化、資本主義文化を批判し、新しい社会主義文化を創生しよう」という社会運動だったが、上層部は権力闘争に明け暮れ、一般人民のあいだでは、それまでの嫉妬や恨みを晴らす機会と化した。多数の死者をふくめ、一億人近くが犠牲となった。一方では、文革が当初めざした思想的理念は、別のかたちとなって今日まで受け継がれているといえる。
*2.下放(シャーファン/かほう):文化大革命の時期に行われた思想教育の一つ。都市部のインテリ層や青年たちを、地方の農村へ強制的に移住させ、おもに肉体労働を通じて社会主義国家建設に協力する良き労働者に改造しようとしたもの。
——————————
紙面版ご購入はこちらをクリック
ひきこもり新聞をサポートして下さる方を募集しております。詳細はこちら
更新情報が届き便利ですので、ぜひフォローしてみて下さい!
Twitter
Facebookページ