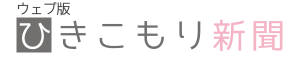『オープンダイアローグ体験記』
オープンダイアローグがひきこもりに対して目覚ましい効果を発揮することが確認され始めている。二〇一七年六月に発売された『精神療法』では特集が組まれ、オープンダイアローグは、ひきこもっていた重度の強迫性障害の女性に対しても有効であると報告された。それは、「一年前には、自殺の危機さえあったことが信じられない」(信田さよこ)ほどの効果だ。『現代思想』二〇一六年九月号の特集でもオープンダイアローグがひきこもりに成果があったと報告されている。この特集において、オープンダイアローグを日本で広めている筑波大学の斎藤環教授は、「個人精神療法で診た場合には社会参加まで通常二年かかるコースが、半年にまで短縮できました」と述べている。この半年で社会参加に成功したケースこそ、斎藤環教授がひきこもりにオープンダイアローグを適用した第一号になる。実は、その適用者が私だ。
そこで、オープンダイアローグを受けてどのような変化が起こったのか述べたい。紙幅の都合上、オープンダイアローグについての詳しい説明は専門家の著作に委ね、ここでは、当事者視点での報告をする。
まず、オープンダイアローグが始まる前の親子の会話は、「説得」や「議論」が中心だった。「説得」は、どちらが屈服し、従属するかが問題となり、どちらも納得しなかった。「議論」はたがいの非をあげつらうだけで、話が噛み合うことが無い。このような親との会話は壁に話しかけるようなもので、独り言(モノローグ)に等しい。きちんと向き合い、言いたいことを言い合っていても、会話はいつも平行線で終わり、変化は生み出されなかった。
一方、オープンダイアローグは「対話」だ。個人が尊重されながら、共有可能な言語が作り出され、合意が生まれていった。具体的には次のような方法だ。まず、筑波大学病院の診察室で斎藤環教授、准教授、父、母、私の計5人が参加した。オープンダイアローグは、①私、②両親、③准教授という順序で斎藤環教授が語り掛けることで進む。①では、教授が開かれた質問(はい/いいえ以上の答えが求められる質問)をして私がそれに応える形がとられる。この間、両親と准教授はただ聞くだけで会話には加わらない。次に、②では、私の意見を聞いていた両親がそれぞれ思うことを述べた。③では、①と②で話された内容について准教授と教授が話し合った。話す機会と聴く機会が丁寧に区切られているのが特徴的だ。

(リフレレクティングの様子。セラピスト同士で話し合い、親子はその話を聞く)
「説得」や「議論」でうまくいかなかったことが、なぜ「対話」であるオープンダイアローグでは成功したのか。それは、自由な発言を許された結果、対話が継続し、当事者自身に変化を起こせる十分な時間と機会が保証されたからだ。
オープンダイアローグでは、専門家から結論を押し付けられることが無い。当事者を「経験専門家」としてとらえる「無知の姿勢」のように丁寧に声を拾い上げて応答していた。この否定されることなく安心して発言できる空間が「対話」を形成した。また、斎藤環教授は上記『現代思想』で、「患者さん自身が主体的に変化するスペースをつねに確保しなくてはいけない」「治療者側の治したいという意図はかえってそのスペースを奪ってしまう」と述べる。当事者の主体性、自発性を最大限尊重したからこそ、「説得」では不可能だった変化が「対話」で生まれたのだろう。
「説得」では結論が先行している。結論が先行しているのならば、ひきこもり当事者は何を言ってもモノローグになってしまう。親との会話を壁と話しているように私が感じたのは、動かしがたい結論が先にあることから生じる無力感が原因だった。このように、ただ一つの結論や答えに収束させようとする「閉じていく会話」では、当事者の主体性や自発性は生まれない。むしろ、当事者を無力にする。「働け」と、ひきこもりを「説得」しても無駄なのは、指示や説教が当事者の力を奪うからだ。
私が受けたオープンダイアローグは、ひきこもり当事者の主体性と自発性を回復させるものだった。また、参加者全員で行われる「対話」は、家族全体の再生を可能にする。今後は、暴力的介入団体が利用する「説得」ではなく、個人を尊重した「対話」による支援が広がることを期待したい。
文・木村ナオヒロ