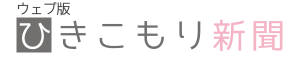ひきこもり実態調査の何が問題か
 (イメージ提供:Shehan365)
(イメージ提供:Shehan365)
(文・割田大悟)
筆者はかつて病気が悪化したことでひきこもり状態になり、何もできない自分に対し、無気力や希死念慮を経験してきた。その当時を思い出しながら現在は横浜で居場所「ひき桜」の運営や「ひきこもりピアサポートゼミナール」の主催、ブログによる情報発信などを行っている。
最近新たな火種が飛んできた。2016年9月に内閣府が「若者の生活に関する調査」を発表し、ひきこもり状態にある人の推計が54.1万人に「減少した」というのだ。すでに各方面から「40歳以上の当事者が含まれていない」「いかにもひきこもりが問題であるような調査」など異論が出ているが、本稿ではひきこもり経験者として自分なりに今回の調査を分析し、考察を述べたい。
国の施策と現状のギャップ
本調査によって明らかになったことがある。それは厚生労働省が各都道府県と政令指定都市に設置している「ひきこもり地域支援センター」がほとんど活用されていないことである。調査該当者が少なくバイアスが生じてしまうが「ひきこもり地域支援センターに相談したことがある人」は、本人が15人中0人、家族が28人中1人だった。このように調査によって実態を明らかにしたことについては一定の意義はあるものの、ひきこもりに特化した機関がこれほど活用されていなかったという結果は重く受け止めるべきである。
社会的自立とは
本調査ではひきこもり群を「社会的自立に至っているかどうかに着目」と述べられている。あたかも「ひきこもり状態の人は社会的自立をしていない」ような捉え方である。これはひきこもり状態の人に対する一面的な捉え方であり、ひきこもり状態にあっても収入を得ている人もいれば、インターネット上で相談支援を行っている人もいる。それにも拘わらずステレオタイプな見方で定義をしているのは解せない。
ひきこもり親和群はもっといる
ひきこもり親和群の実数について記載はされていないが、報告書に基づく計算によると約170万人にのぼると推計される。しかし親和群の定義にも疑問がある。なぜなら問32の13~16の4つの問いに対し「すべて“はい”」または「1項目のみ“どちらかといえばはい”」回答した人のみが親和群と定義されている。つまり実際には4項目とも“はい”“どちらかといえばはい”と回答していても、そのうちの一部は親和群の定義から除外されているのだ。よってひきこもり親和群は調査報告より多くいるはずである。
現場で使えなければ意味がない
本来実態調査というのは「調査によって得た知見を現場に還元すること」を目指すもののはずだ。しかし膨大な量の報告書を当事者・家族・支援職が活用するのは困難だ。報告書を出すのであれば考察を述べたうえで「何を明らかにしたのか」「調査がどのように役に立つのか」を分かりやすい形で解説しないと現場では使えない。このように「現場に歩み寄る配慮」がなければ調査結果と現場の実態はますます離れていくだろう。
当事者の声を反映した実態調査とは
ではどのような調査が求められるのか。それは「ひきこもり当事者の声」を反映したものである。そして当事者の声を反映するには「事前のヒアリング」が必要不可欠である。どのような状況で日々を生き抜いているのか、どのような生きづらさを感じているのかを聴き取り、意見を反映したうえで調査を立案しなければならない。そのためには積極的な情報収集に努めたうえで「何が問題なのか」「現状の支援体制で何が不足しているのか」を予測したうえで調査を行うべきである。
当事者目線の再調査を
最も重要なプロセスは「ひきこもり当事者・経験者の参画」である。具体的には委員の中にひきこもり当事者・経験者・家族・専門職・外部関係者など多方面よる人材を選ぶ必要がある。ただしひきこもり当事者・経験者を“形式的に”委員として選出してはならない。当事者・経験者委員に対し、調査票作成や調査方法に関して十分な説明をしたうえで「どのような形であれば回答をしやすく、最も実態に即した回答が得られるか」を連携しながら検討する必要がある。以上のことから40代以上を含めるだけでなく、ひきこもり当事者の声を「具体的に反映した」うえで再調査を行うべきである。