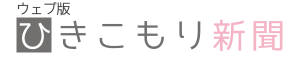(文・ニャロ)
三十年前の正月に決行した”あること“
あれは三十年近い前のお正月の事である。
私は、世間様が里帰りして過ごすと言われる年末年始の期間、引きこもるというよりは隠遁生活なるものを決行した。
意図的ではあるがやむを得ずなのだ。
一階に大家の若いファミリーが暮らしている、二階の一部屋に、私は賃貸契約で住んでいた。
二階には全部で四部屋ある。地方都市で、残りの三部屋は学生の一人暮らしばかりであった。冬休みが始まると、夜も人が帰っている気配がなくなり、クリスマスを越えるあたりからは、私の部屋以外、どこも長期留守の様子となった。
いよいよ始まる一人帰省偽造工作
ドタバタと慌ただしいドアの開閉や、友人を連れ込んでの酒盛りもなくなり、火の消えた釜戸のような静けさの中、耳を澄ますと階下から大家一家の楽しげな笑い声や、母親のちょっと声を荒げた叱責などが響いてくる。
夜中に野良猫が鳴きかわす。
通りで車の行き交う音。
それらが妙に耳につくようになると、いよいよ息をひそめる恐ろしい時がやってきた事を悟るのだ。
今から振り返ると、それはお笑い草でもあり、反対に厳かな修行でもあったようにも思えるのだが、当時の私には、生きていくためにはやりおおせなくてはならない、自分から自分への戒厳令であり、厳守せねばならない処世術であった。
今でこそ「自己評価が低かったのだ」とくくることも出来るが、そのようなこましゃくれた言葉も価値観も、まだ持ち合わせて居ない、世の中に一人で対峙していかねばならない若い未熟な人間であった。
これまた当時は自覚も無かったのだが、成育歴や教育を受けていく中で培われた、このような盲信が私の中に巣食っていた。目立ってはならないし、変人は弾き出される。私は良く社会適応できている、人好きのする、いや人好きとまでいかなくても、せめておかしな人では無いことを見せておかなければならない…。
任務内容『アパートを追い出されないように”普通”を装う』
私には帰省する場所が無かった。つまりアパートを追い出されたら即時ホームレスとなる。心の拠り所にも、相談する人間関係にも、暫しをしのげる資力にも無縁だった。
周囲に適応した人間であることを示す努力を惜しまない一方で、私は疎外感をまとってしか世間に居合わせることができなかった。
まとっている疎外感は目に見えないのだから、私は良い返事、にこやかな笑顔、好印象の挨拶で、周囲の目を看破しては部屋に戻り、本来の自分に戻るべくアルコールで消毒する日々だった。
部屋とお酒が、私を私でいさせてくれる。
そんな自分の大事な人目にさらされない基地を、死守しなければならぬ。もしも何らかの失態によって取り去られてしまうことだけは避けなければならなかった。
私は社会に良く適応している良き若者なのだから、同世代の皆様が帰省なさったなら、私もそうしているべきなのだ。
しかし帰省先がない。考えるだけで身の毛もよだつような話ではあるが、私の実家はDV家庭で、寄りつく気など毛頭ない。ところが、当時「DV家庭」という言葉すら存在しないことが、私に負荷をかけていた。
正月に帰省しない、あるいは帰省先の無い、わけありの若者。それは笑い声の絶えない階下のご家族からは「おかしな人」というレッテルを貼られるのに十分であると思われた。
もしかしたら私自身の気づけない、あるいは気づいたら生きるのが大変になるため知らんぷりしていた寂しさなるゆえもしれないのだが、二階の住人が居なくなり、階下の物音が私の部屋の中にまで浸透して、部屋とアルコールに守られた居城が脅かされているように感じ始め、私の耳が集音機のように研ぎ澄まされ、音々が私の心の防壁をつつき出す。
いながらにして帰省した者になる
私はいながらにして他の三部屋の住人さながら帰省した者となる。当たり前のおかしくない若者達が帰省したのだから、右に倣えと私も帰省した事をアピールするのだ。
その年の正月は貯金も手元の金も尽きており、電気、ガス、は停められていた。私が今でも有り難さを噛み締めるのは、水道だけは何度も「止めます」と通告が来たにも関わらず、何故か止められていなかったことである。
私には、水道は社会との命綱だった。そっか、私には生きていて欲しいのか?
さて、帰省したはずの二階から物音や人の気配がしてはならない。私はコトリとも音を立てず、そろそろと水を汲み、細心の注意を払って数日に渡る部屋籠りを決行する。
鼻水ひとつすすらない。スローモーションのように足を忍ばせる。息を潜めて天井を眺める。私にはよくナチスの虐待にあった手記などから勇気を得る習慣があった。あー、私はなんて幸せなんだろう。屋根がある。
私を虐待する者、殴りにくる者はいない。私は逃げおおせ、避難に成功し、自由の身なのだ。私は密かにこの幸福を反芻する。
しかし、居ない居住者という矛盾を演じきるのには問題があった。トイレだ。手動消音ではないが、音を消し流さないで過ごす。
そして石鹸まで美味しそうに見えてくる
いくら静かに幸福を味わっていようが腹は減る。食べ物らしき物は何もない。冷たい水を飲む。サバイバルしていると、日常では放置していた思わぬ忘れ物に思い当たる。
確か以前、母親から送られた海苔が缶の中に手付かずのままあったはずだ。ソローリソロリと部屋の隅の缶を探し当てる。海苔、立派な食べ物だ。
何せ腹が減ると石鹸まで美味しそうに見えてくる。海苔なら正真正銘のご馳走だ。はやる胸を押さえて、ソローッと音を立てずに缶を開ける。口に放り込む。一抹の落胆が私を呑みこむ。期待した味と違う。
そう、それは調味料のついていない焼き海苔で、何というか味が思っていたようにはしないのだ。長年放置されたため風味も落ちていた。それでも噛んでいると先ほどの落胆はどこへやら、食べているという確かさが喜びに変換されていく。私は満足だった。
――そして今
貧乏と世間様への過度な気遣いというダブルで迎えた年末年始は、その年がピークだったかもしれないが、お正月というと似たり寄ったりな時が多かったように思う。虚勢を張って生き延びようと苦闘した日々。
今は価値観の多様性の中で、悠々自適に過ごしている。引きこもりと言われようが変人といわれようが親不孝と言われようが、親切心に満ちたお節介の数々に対して、相手が信じて止まない価値観を無下にしないように受けている。
何よりも私は私の勝ち取った選択に花丸なのだ。
世間体を恐れ、世間様を私よりも大上段に掲げ、疎外感をまとい、戦術を練っては撃沈し、消耗していたが、たとえ多勢に無勢であったとしても、私は私、あなたはあなた、そして同じ時代を呼吸する私達なのだから。