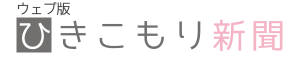(文:ぼそっと池井多)
「私が証明です」
前回「ひきこもり放浪記 第2回」に、「1980年代のひきこもり」と副題を打たせていただいた背後には、私のこんな体験がある。
ひきこもりやニートという言葉が、ひどく悪いイメージとともに社会に蔓延しはじめた2000年前後のこと、このように解説している経済評論家がいた。
「バブルがはじけ、若者にとって就職氷河期が到来したことにより、就職で挫折した若者たちが多くひきこもり、日本は初めてひきこもりという社会問題をかかえることになった」
2000年当時は、ひきこもりの概念がはっきりせず、まさか自分もひきこもりだと思っていないから、「そんなものか」と思って読み流していた。そのため、論者が誰であったかも思い出せない。
いま思い返せば、とんでもない説だと思う。
バブル経済がはじける前からひきこもりはいた。
他でもない私自身がその一人であった。
そのことに気がつくのに、しばらく年月が必要であった。
いま、私はこの経済評論家の自信たっぷりな説を否定する。
むかし
「私が証明です」
とかいう化粧品の宣伝があったが、
まさに「ひきこもり発生バブル崩壊説」を否定するのに、
「私が証明です」。
経済的活況から恩恵を受けられない
私が23歳で最初にひきこもりを発症した1985年は、まさに日本がバブルの階段を昇り始めているころであった。
しかし私は、エネルギッシュなこの時代から何か恩恵を受けたという感じがしない。
大学の仲間などは、
「就職活動で、先輩に社費でステーキをおごってもらった」
などと語り、それをもってバブルからの恩恵に数えたりしているが、私の場合、ステーキはおろか、焼き鳥一本もおごってもらえなかった。えーん、えーん……
ってか、いやいや、そういう問題ではないのだ。
当時の一部の企業で見られたとおり、ステーキどころかもっと高額な接待までしてくれた としても、私の充たされない感覚は何ら変わらなかったであろう。
それどころか、私は自分を取り巻く経済的活況に圧迫されていたのである。
「そんなもの、なくてもいいじゃん」
と思う商品がショーウィンドウには満ちあふれ、
「それを持ってないとカッコわるい」
というだけの理由で人はモノを買いにいった。
人々は朝から高級デパートに行列を作り、
そこでお買い物できるだけのお金を懐に持っておくために、
人はシャカリキになって稼いでいた。
そういう状態が、
「私は仕事してる」
なのであった。
いっぽう、シャカリキになって稼ぐために、
本当はなくてもいい商品をあれこれとひねり出し、
人の思考をだまして購買意欲をかきたてるために、
あれこれ歯の浮くような言葉を並べたて、
生産するために地球環境を壊し、
販売するために人間関係を壊し、
労働するために自分の健康を壊し、
ありとあらゆるものを壊して成り立たせているのがバブル期の 経済活動であった。
「なぜ、自分もその中へ入っていかなくてはならないのか」
という疑問が、私の内部ですさまじい渦を巻いていたのだと思う。
その中へ入ったが最後、会社の奴隷となり、
砂を噛むような仕事に精力をすり減らし、
「そろそろお前も身を固めることだ」
などと圧力をかけられ結婚をし、
毎日往復四時間も満員電車にゆられて給料を会社から家に運搬し、
「日本の少子化が進んでいいのか」
などとせっつかれて子どもをつくり、
ベロベロバーをしているうちに、
縁もゆかりもない地方や海外を転々と飛ばされ、
気がついたら定年を迎え、私は寝たきり老人になっているのではないか。
そんなことをするために、自分は生きているのだろうか。
そんなことをするために、自分はこれまで
中学受験だの、大学受験だの、
数々の受験へ母親から尻を叩かれて、
苦しい思いをして前半生を送ってきたのだろうか。
私は鬱々とした自問自答を繰り返していた。
「お前はただの怠け者だ」と責める内なる声
しかし、それらは言葉となって口から出てくることはなかった。
言葉になりにくい思考であった、ということが、まずある。
それに、そんなことを口に出したら、これはまたえらいことになりそうな予感がした。
「お前は労働の尊さがわかっていないな」
「人はみんな苦しい人生を生きているんだ」
「働かざる者、喰うべからず、だ」
などと、これまで何千回聞いてきたかわからない
古典的なお説教をされるのが関の山であることは、
容易に予測がついたのである。
また、私自身も
「仕事そのものがくだらない」
などとは、逆立ちしても思っていないだけに、
なおさら葛藤は自分の奥へ押し込まれていった。
駅のトイレの清掃係の方などを見かけると、
「どんなに単純に見える仕事でも、
こういうふうに仕事をしてくださる人がいなければ、
この社会は回っていかない」
ということを骨身にしみて考えさせられ
「自分は怠け者だ。とんでもないろくでなしだ」
と己れを責める言葉が頭に湧いてくるのであった。
しかし、だからといって、
自分自身がそういう職業につくことが、
あるべきかたちであるとは、どうしても思えなかった。
誰か他の方々がそうした仕事をやっているかぎりは
崇高な作業として頭(こうべ)を垂れるのだが、
いざ自分がその仕事をやるとなると、
なにか自分が生きている時間を無駄づかいする単純労働に思えて、
たちまち「何かちがう」と感じてしまう。
この矛盾を自分でもどう説明してよいかわからず、
私は煩悶を深めていった。
周囲の友人を見ると、
誰一人そのような悩みは抱えておらず、
経済的活況を楽しんでいるように見えた。
こうして私は、バブルで渦巻く日本の中でますます孤立し、
どんどん精神的にひきこもっていったのであった。
(「ひきこもり放浪記 第4回」へつづく)
ひきこもり新聞を応援するにはこちらをクリック